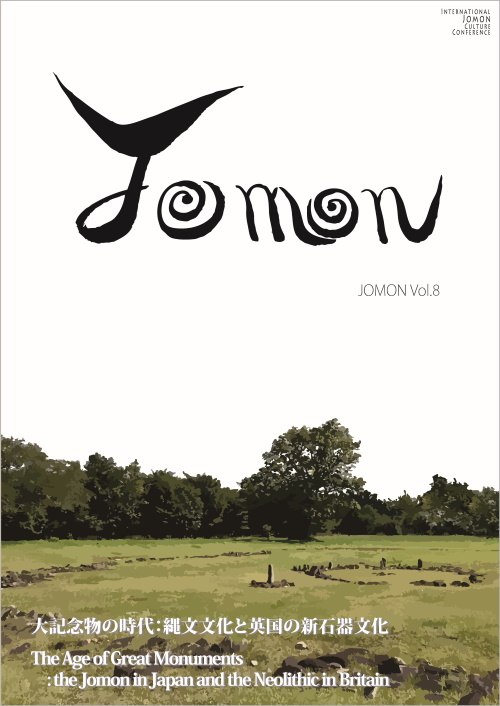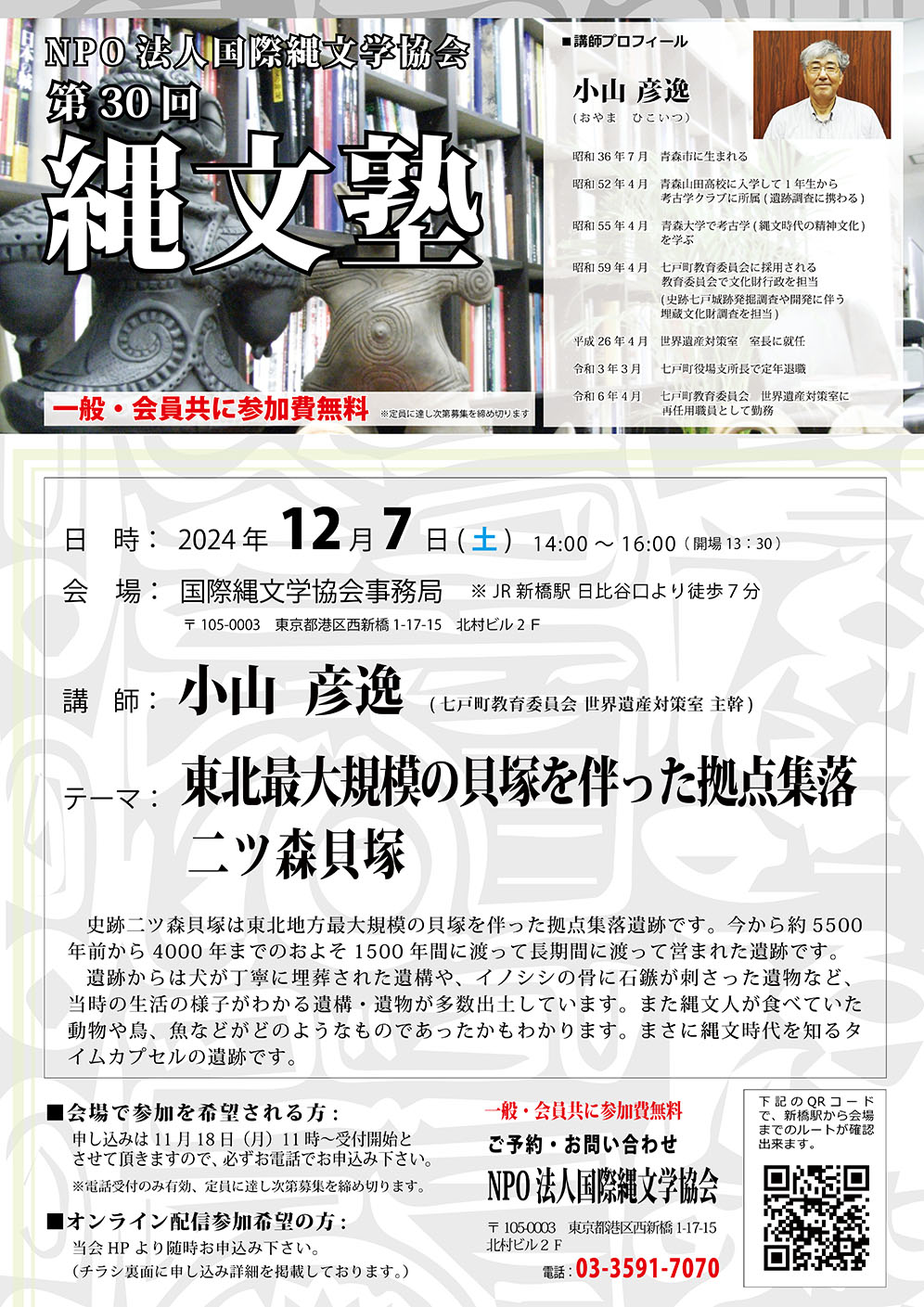■ 『縄文時代の信仰について・3』 菅田正昭
では、神のカは何か。神のカはここに書きましたように、ケの音韻交替である。これがさらに音韻交替をするとキ(木)になるわけです。ミは祗。ヘビのミ自体で神というか、そういう意味ももちろんあるわけです。日本書紀の「一書(あるふみ)」(身代下第九段第二)天孫降臨の一番冒頭のところに〈アマツミカボシは邪神である〉というふうに出てくる記紀神話の中で、唯一邪神という言葉で登場するアマツミカボシという神様がいるわけです。正確に引用すれば、「天に悪しき神有り。名を天津みか星(あまつみかぼし)と曰ふ。亦の名は天香香背男(あまのかかせを)。」です。これは常陸のたぶん先住民の神様のと思われる神様で、天にいるミ(祗)、厳しい(いかめしい)と同じで、天に輝いている星神だというふうに言われている、そのミカボシのミでもあるわけです。
ケの方ですが、「ケの民俗に注意」と書いておきましたが、このケというのはミケツガミのケです。トヨウケのケです。ウカノミタマのウカのカです。要するに食べ物のケです。私が住んでいた青ヶ島では、アサケ、ヒルケ、ヨウケと言った。朝御飯はアサケ。昼御飯はヒルケという以外にヒョウラという言葉を使う。これは兵糧という言葉から、武士の兵糧になってしまいますが、食べ物はケ、そういうケを今でも使っています。そのケと関係があるのが、ミケツカミのケであり、酒(サケ)のケなんです。酒のサは、沖縄のサバニなんかも含めて日本語では小さいとかいう意味になるわけですが、その他に「純粋な」と言う意味が含まれています。ケのもっとも純粋なエッセンスが含まれている飲物だから酒になるわけです。そういう酒のケ。それからケが残っている言葉としてはハタケ(畑)もあります。この言葉もすごく古いわけです。おそらく縄文時代に田と言う言葉があって、このハは端、田圃の端っこで食べ物を作るからケ、それで畑なわけです。ケは万葉集では有間皇子の歌で、「家にあれば 笥(け)に盛る飯(いひ)を 草枕 旅にしあれば 椎の葉に盛る」ってあります。つまりケを容れる入れ物もケです。そういういろんな意味を持ったケがあるわけです。そのケはもともとはどういう意味かというと、――気という字をあてる――生命力を意味するわけです。食べ物というのは生命力の源であるわけです。だからケなわけです。生命力の源が無くなることもそうですけれど、それを食べられなくなった状態がケガレなわけです。ケ(気)が枯れるわけです。穢れ。ケガレ観というのが変遷してきて、悪く捕われてきてるわけですけど、本来のケガレというのは生命力の減退している状態をケガレというふうにいうわけです。そういうケです。 それからこの木(き)は漢字ではないかと思っている人がいますけど、漢字の方はモクですから、これは日本語のキなんです。木も広い意味じゃケの仲間というか、木なんです。食べ物がケだというのは食物になる食べ物になる動物という獣がケなわけですし、今はあまり言わないみたいですけど、私なんかが小学生の頃なんかにはよく当時の社会科で、一毛作、二毛作というときの毛、あれはなんでケが出てくるかというと。本来ケなんです。そのケを当て字で漢字の音でいうから毛(もう)になるわけです。少し話が飛びますが、毛を二つ重ねるとどうなるか――「毛毛」をなんと読むか。ケケじゃないんです。この毛がひらがなになって、「もも」。「驚き・桃の木・山椒の木」の桃。桃もケなんです。果物の中の果物という意味で、モを書いたわけですよ。だけどそれが漢字に元に戻っちゃうと毛毛になっちゃうわけですけど、ケの中のケという意味で書いてそれが桃になっているわけです。そういう意味では群馬県、栃木県、一部埼玉とか、現在の茨城の一部まで含まれているわけですけども、毛の国。上野(かみつけ)、下野(しもつけ)のけ。ですね。あのけもけなわけですね。それは食物系なのか動物系なのかというのはよくわかんないですけれど、上野、下野というのは古代においては非常にケの豊富な所であったということでついていると想像できるわけです。勘違いしてケと書いてあるからアイヌ系の毛深い人がいたからだろうと思っちゃう人もいるようですけど、そうではないということになると思います。そういうケの音韻交替が神のカであると。それとミというヘビに象徴される不思議な生命力ですけど、それに合わした物が神という語源にたぶんなってくるというふうに思うんです。たぶん同時発生的にどちらが古い、どちらが早いというのはわかりませんけど、そういうことになります。ただ、言語学的に考えるとアイヌ語と縄文語というのはかなり離れてるだろうということで、その縄文人はアイヌ説で採りたい人にとってはオーストロネシア語説というのは非常に不利なことになると思うんですが、でも、もっと遡ればかなりどこか近いのではないかと思います。ヘビが何度も脱皮を繰り返す不思議な生命のあるということに非常に注目したのがニコライ・ネフスキーなんです。 ニコライ・ネフスキーという人について、折口信夫は「青い目をしたロシアの異人さんだけど、日本人より日本のことをよく知っている」というふうに言っています。しかしたぶん1943年か4年に生死不明になってしまう。それで、ソ連邦が崩壊した後ハッキリしたこととしては、ニコライ・ネフスキーはスターリンによって粛清されてしまっているということになるわけですけれど、ニコライ・ネフスキーが大正時代、日本にかなり長い滞在をし、日本人の女性と結婚して一緒に連れ帰って、ネフスキーの娘さんが生き残ったらしいんですが、その人も亡くなって、ネフスキーの孫に当たる人が今もロシアに健在であるらしいです。そのニコライ・ネフスキーが、非常に早い時期の沖縄でのオモロの研究家なんです。実際に八重山なんかに調査に出掛けて、聞いたままにローマ字で書いています。そのことによって当時の八重山の人たちがどういう八重山方言を使っていたのか、という言語資料として残されたわけです。その当時は、誰もそんなことをしていないので、非常に注目されていましたが、そのネフスキーがヘビのことについて書いています。そのヘビというのがネフスキーの『天の蛇』なのですが、それは実は虹なんです。この虹のことなのですけど、ヘビのヌシ、大物主とか沼の主などという言い方をしていますが、ヘビのことを主とも言うわけです。ニフライ・ネフスキーは虹nijiと主nusiというのは語源的にはたぶん同じ源ではないかというふうに推測しています。ネフスキーが注目しているのは実はヲチミヅ=変若水です。ヲチミズのことを普通ワカミヅ(若水)とも呼ぶわけですが、お正月に若水を汲むということをいうわけです。この若水は、泉や川、井戸などから1年で1番最初に汲み上げてくる清水です。ヘビはそれを飲んで若返るんだということをニコライ・ネフスキーは『天の蛇』という本の中で言っております。ネフスキーの『天の蛇』は面白く非常に魅力的な良い本なんですが、この本を見て、私は縄文人の蛇信仰というのは実は不死性といいますか、死なない、何度も死にそうになっても甦ってくる、強力な生命力を持った脱皮をするものとしての蛇だというふうに思ったわけです。その辺のことは藤森栄一は大地母神という形で捉えているわけですけど、私は再生の神なんだというふうに思っているわけです。さきほど、木がの話もしましたが、『東日流外三郡誌』が偽書であっても、アラハバキ自体は存在したわけです。このアラハバキのハバですね、これはハハではないかと言われています。このことについて吉野裕子さんがアラハバキというのは実はヘビが御神木のてっぺんに絡み付いてる状態をアラハバキというんだという説を唱えているわけです。そういう意味では確かにアラハバキというのはヘビ信仰に関係してきますし、アラハバキ神というのはなぜか産鉄地帯と非常に関係があるわけです。ヤマタノヲロチ伝説もそうでした。縄文時代とか、今までの鉄というのはずっと後の、日本においてはずっと後だと言われているわけですけど、いろいろ考えてどうもかなり古くから鉄文化があった可能性もあるんではないかなと思うんです。ちなみにアラというのは、荒々しいアラです。新しいのもアラタというアラなんです。要するに生命力の一番甦った状態、ウブな状態、これを要するにアラと言うらしいのです。『常陸風土記』とかさっきから言っていますが、常陸にかかる枕詞アラレフルなんです。アラレフルとうのは、霰がぽつぽつと降って来たという霰でもあるわけですけれど、それだけではなく、要するに神々の甦る場所としてのアラといいますか、そういうものがあるわけです。
次へ>