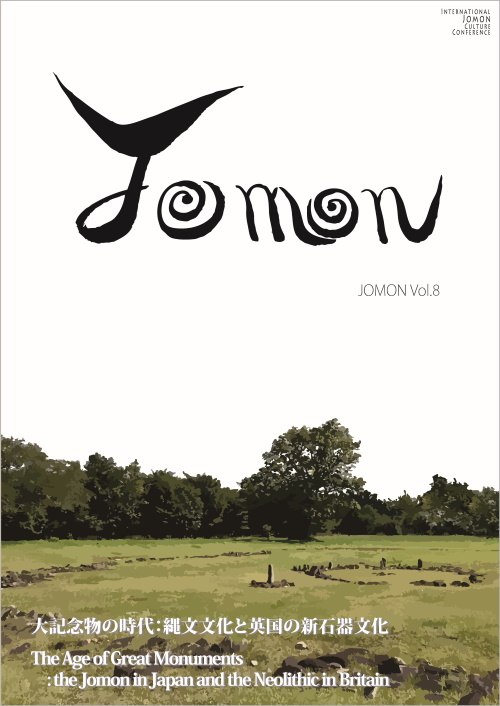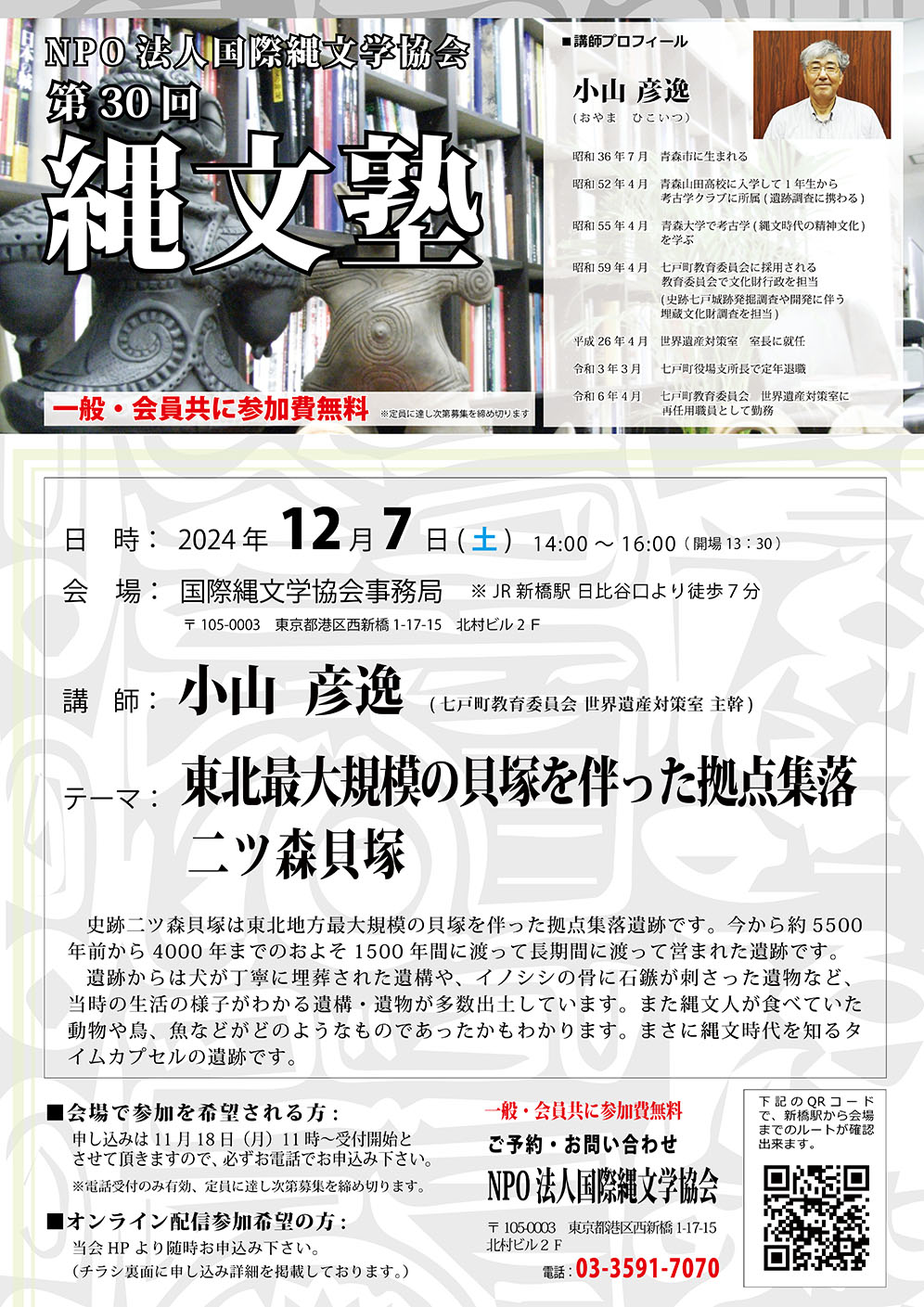■ 『日月を放つ縄文の巨木柱列・3』 萩原秀三郎
さて、三内丸山人はいったい何を食べていたのでしょう。縄文の文献を読むとドングリのことばかり書いてありますが、北海道大学で検査をしたところ、半分以上栗を食べていたと言う事がわかった。確かに三内丸山には栗林があり、明らかに栗を栽培していたことがわかりますが、これは大変な結果です。一般的には、ドングリと言われてきましたが、栗が主食で、あとは稗、魚介類や動物の肉だったと。しかも縄文中期は二~三度気温が下がって、栗がよく実ったらしいです。
以前、太平洋側の六ケ所村に居た方に、栗の採り方を伺ったことがあります。子どものときに家族総出で、一mくらいの大木がたくさんある国有林に栗拾いに行ったと。採るのには、必ずリーダーが必要で、その人の合図によって、枝に綱をかけて、一斉にわーっと引くのだそうです。そうすると信じられないでしょうが、台風並に音がして、ものすごい量の栗が落ち、地面が全く見えなくなると。もちろん栗で怪我しないように、頭に綿帽子のようなものを被ります。リーダーの良し悪しで、作業の良し悪しも決まるようです。
保存方法ですが、先に茹でてから保存すると、全然美味しくなく、天日干しをして乾燥した状態で保存して、食べる時に、二~三時間かけて茹でて戻すと、採ったときと変わらない同じような甘さですごくおいしいんだそうです。当然、縄文時代だったら作業場で粉にして縄文クッキーみたいなものを作ったりしたと思います。
このように栗というのは、自分たちの命を預かる神樹というわけです。例えば霊魂がどういうふうにして出てくるかというと、今の場合でしたら、いわゆる力餅や力うどんとか、あれは命を支えている力、エネルギー源です。穀物というのは、エネルギー源があるために温かい。亡くなると身体は冷たくなります。これはエネルギー源がどこかに飛び去ったことです。栗の場合も、大変な霊力を持っていたと思われます。
人間と言うのは、どこから生まれたのか。桃から生まれた桃太郎とか、竹から生まれたかぐや姫とか、甘栗太郎、こういう話はいっぱいあります。植物から人間が生まれたという話は、特に東南アジアからオセアニア、太平洋の南の方まで渡ってあります。ヨーロッパですと、全部神様が作ってしまいますが。ユダヤキリスト教、日本の場合はみんな物がなっていくわけです、中国でいうと、ミャオ族だったら風香樹という木から祖先、始祖が生まれています。そして、亡くなったら、やっぱり風香樹に帰るためにお棺を風香樹で作る。そういうふうに、いわゆる植物から生まれた感覚があるものだから、おそらく三内丸山でもそういう感覚があったかもしれません。栗の木を使って柱を立てているのですから、そこに覆いをするなんていうのはもってのほかです。神樹というのは仰ぎ見るものです。
そして、例えば現代でも紀の国、紀州のいろんな地域では、空神様というのがあります。神樹を御神体としているところがたくさんあるんですが、そこは、絶対覆いをしてはいかんと、罰があたると言われています。やはり空神様なのだから、呼吸をしているのです。天と地と、それを繋いでいるのがアンテナである柱。そういうことを考えると、神殿説なんていうのは、全くナンセンスだと思いますが、考古学の方では圧倒的に神殿説の方が多いです。
太陽霊が寄り付くという意味では、折口信夫さんの論文『髭籠の話』で、『髭籠』とは神の依り代であり、例えば山車は、本来太陽を依りつかせるには山や柱が中心であって、あのように、引きまわる山車のようなものが生まれたと。古代においては、もちろんいろんな神霊は、たくさんいるけども、誰にでも、すぐにわかったのは、太陽霊ではないかと。太陽霊が寄りつく柱というのを、オギシロといいます。オギシロというのは招く、人間の側から言えばオギシロで、あちらに言わせれば、依り代なわけです。けれども、この中国の、いわゆる東アジアの感覚で言うと、太陽霊も月も星も、古代は地底に住んでいるんです。それで、どこから出て来るかというと、東の端の木から昇ってくる。それで梢の先から、ぱっぱと出てくるわけです。夜はもちろん、星も梢の先から、まるでクリスマスツリーみたいなものです。それで、日が昇る朝になると、太陽は根方から伝って、梢の先からひょいと、次から次へと出てくる。
日々、月が形を変えるように、太陽も毎日形が違います。だから、一個の太陽だとは思っていなかったのです。毎日毎日、太陽を別なものだと思っていました。多いところは九十九とか、民族によっていろいろですけども、少なくとも十は考える。殷代は、それに名前を付けて、甲日、甲乙丙丁、いわゆる十干というのは、干支(かんし)といいます。支は、もともと枝だったんです。甲乙丙丁、十日で一巡する、一巡り。これが旬です。日のまわりを囲ってるのが旬。上旬、中旬、下旬と。太陽が、毎日東から出てくる。そういうふうに地底から、太陽も月も星も、地底では熱い太陽がほとぼりを冷ます必要があるから、水の中をくぐりぬけると。水脈があって、木が水脈を吸い上げます。根方から太陽が樹木を昇っていく、順番を待っているんです。
これを鳥の形で表したのが、三星堆の鳥です。十くらい止まっていました。つまり、鳥というのは飛び立つものだから、そう考え出した。太陽が三星堆の場合でも、地底の水脈を龍、こういうものを描いた。天と地上と天空と、普通は分かれていて、世界樹の樹を分解していくと三層から九層になったり、十三層になったり、いろいろあります。
少し脱線しますが、藤原京にしても、久米寺、飛鳥寺は、みんな基本的な伽藍配置です。真ん中に塔があって、本堂や講堂、金堂に仏さんがお祭りされていた。周りに重点が行く前は、塔が中心でした。塔というのは死霊を、死体をお祭りしたところです。墓から始まって、仏舎利、それで、五重の塔というのはだんだん後の時代になると、金堂と並んで、講堂全体の横に来て、それから、当麻寺とか、東西薬師寺でもそうですが、東大寺になると、伽藍の外へ出ています。今はないですが。
このように、だんだん装飾化して、中心にあったものが周辺に飛んでしまうのは、これは、どこでもそうだと思います。今、柱のお祭りが境の領域で行なわれていようと、どこに塔が立っていようと、柱というのは中心の意味があるということです。ですから、その柱で太陽の昇降、上り下りを司っているのが、シャーマンです。シャーマンというのは、世界の秩序を整えるという役もあります。例えば天照大神は、機織りをやっています。機を織るということは、どういう意味かと言うと、神楽の採り物として出てきます。神楽の採り物とは、舞うときに手にとる榊とか、剣や弓の事です。そういうものは、どういう意味を持っているかというと、巨木をミニチュア化した、小アンテナ。つまり、小さなアンテナを持ってみんな舞っている、ですから神を呼ぶものです。そのときに、機織りの道具を持って踊ったのです。これを神楽の場合は、宝物、あるいは茅宝(かやだから)といいます。茅が宝なのです。茅というのは、イネ科の植物で、原始の植物、地上で最初に生えてきた植物というふうにいわれています。こういうものを手にとって踊る。つまり採り物としては草です。これを手草、これが神楽の採り物になる。その採り物の原型の手草が巨大化して巨木。つまり世界を一手に掌握するんです。巨木にカミナリさんが落ちるのは、つまりアンテナだからです。
巫子舞というのがあります。巫子舞はどういう形を取るかというと、その場で同じ場所で、回って回り返すんです。これが基本形。それがだんだん発達してくると、少し大きく回ります。出雲神楽とか、あるいは三保神社でも、同じ場所で回って回り返すのではなくて、やや円形を描いて動くようになってきます。回り返すとは、混沌を呼んでいます。なぜ、わかったかというと、中国のシャーマンが、回って回り返すことを、同じ場所でやっていて、それは大変なんです。なぜかというと、一方方向へ回っていればいいものを、逆周りしなくてはならないので、時々よたよたしてしまう。歳取った人は、大変です。なぜ、一方方向に回らないんですかと言いましたら、そんなことは出来ない。昔からやっていて、これは混沌を呼んでる、つまり、あらゆるものの原点に立ち返っているんだと。そこへ行かないと、シャーマン儀礼は成立しない、つまり巫子舞は成立しない。それは、やっぱり中心にあるのは、柱なんです。柱を回るという儀礼は、必ず天体の運行と関係がある。だから巫子舞や、シャーマニズムの原型は、回って回り返すこと。それが、どんな日本民俗学のシャーマニズムの本にも書いてありません。まったく不思議千万です。それが無ければ、つまり神がからない、つまり託宣をするまでに至らない。神を呼ぶためには、必ず、道教の方でも、そのことがちゃんと書いてあります。道教の太鼓の模様、これはつまり、右回り、左回りの、根本を教えています。陰陽以前の混沌を、ここから陰陽に分かれて、いろいろ始まるんです。中国東北に行って、シャーマンに聞いたら、そういう説明してくれたので、ここに全部あるのか、参ったと思いました。ところが日本以外も、世界のシャーマニズムの本はいっぱい出ていますが、1つもそのことは書いていない。現地のシャーマンに聞いて、ようやくわかったわけです。いつも回って回り返している。天地創造の一番始まりに、いつも立ち返ると。
そして、面白いのは病気治しのときです。病気治しにシャーマンが、天地創世のお経をやります。つまり時間が元へ帰る、何も無いところに帰るから、病気が治ると言っていました。それで、はたと思いついたのは、日本の厄年の人が、どういうことをやるかというと、厄を払うために、二月とか三月頃にお餅をついて、お正月をやるんです。それで、もう厄が済んだと。つまり始まりの時間へ戻すから、厄などは、飛んで行くと。非常に古い感覚の、伝統的な伝承的な頭の持ち主が、そういうことをやる。どこへ行っても同じです。
巫子舞の原型がシャーマニズム、朝鮮半島に行ってもそうです。必ず託宣をする一番有効な神がかりの手段とは、技術として、回って回り返すことにあるんです。それをやらなければ、誰も神がからないんです。旧満州へ行っても、内モンゴルへ行っても、全く答えは同じです。
自然と言うのは円環しています。いわゆる歴史的な時間と言うのは、西洋的な思考方法で行ったきりで戻ってこない。ヨーロッパ的直線的時間ではありません。ところが、日本の年中行事を見たら同じことをいつも繰り返しています。円環しているんです。円環しているということは、時間がいつも行きっぱなしではなく、正月を迎えるときに、始めの時間に戻っている。それまでの時間というのは、全然縁もゆかりもない。全く新しい、あらたまの年が始まっているんです。だから目出度い。穢れた時間はさよならということで、そういうふうに、いつも一年ごとに円環しています。それを、お祭りの場合は大変なので、七年に一回とか、二十年に一回とか、規模を大きくしてやっていますが、本来は御柱にしても、一年ごとに魂が更新されるべきものなんです。円還的時間というのは、一年が基本です。それでこの場合、時間を更新、円環させるために、柱が必要だけれど、その柱の元で、司祭し、お祭りをやっているのが、アマテラスさんとか、機を織る人とか、秩序を織りなすのですから、シャーマンなんです。ですから、必ず岩根御柱の元には、シャーマンがいたわけです。例えば、伊勢の場合だったら、斎宮がいるわけでしょう。それで諏訪だったら、大祝がいてシャーマンがいるわけです。出雲大社だったら、国造(こくそう)という、本来は土豪みたいなものです。つまり、こういうものは柱の元にいて、神霊を管理していたわけです。神霊の蘇りを。では、このあと、写真で詳しく説明致します。
次へ>